「最新CPUは16コア24スレッド!」「PコアとEコア、合計20コア超え!」
毎年のように発表される、圧倒的な多コアCPU。その数字の暴力に、我々はつい「コア数が多いほど高性能で、あらゆる作業が快適になる」と信じてしまいがちだ。
しかし、もしPCの主な用途が最新ゲームのプレイや日常的な作業であるなら、その判断は大きな間違いである。
結論から言おう。現代のPC利用者の9割にとって、CPUは8コアで十分だ。 それ以上のコア数は、特定のプロフェッショナルな用途を除き、性能を発揮できないばかりか、思わぬ落とし穴にはまる可能性すらある。
この記事では、なぜ16コアCPUやIntelの大量のEコアが多くの人にとって不要なのか、そしてPCの真の性能を測る上で「コア数」よりも遥かに重要な「ある要素」について、徹底的に解説する。あなたのCPU選びの常識は、根底から覆ることになるだろう。
目次
なぜ「8コアで十分」と断言できるのか
現在のPCの使われ方を冷静に分析する必要がある。
- PCゲーム: 最新のAAAタイトルであっても、その多くは6コアから8コアを最適に利用するよう設計されている。ゲームエンジンは、メインの処理を特定の数コアに集中させ、残りのコアをOSやバックグラウンドタスクに割り当てるのが一般的だ。16コアCPUを搭載しても、ゲームプレイ中のCPU使用率が50%に満たない光景は決して珍しくない。重要なのは、少数のコアがどれだけ高速に動作するか(クロック周波数やIPC)であり、コア数がお祭り騒ぎのように増えても、フレームレートの向上には直結しにくいのである。
- 日常的な作業: Webブラウジング、動画視聴、Officeソフトの利用といったタスクは、せいぜい2〜4コアもあれば快適にこなせる。バックグラウンドで多くのアプリケーションを起動していたとしても、8コアCPUであれば余裕を持って対応可能だ。
もちろん、これは「多コアCPUが全く無意味だ」と主張したいわけではない。その真価が発揮される、特殊な世界が存在するのだ。
多コアCPUが真価を発揮する「全コア・フルロード」という世界
では、どのような作業なら16コア、24コアといったCPUパワーを完全に使い切れるのか。それは、処理を無数の小さなタスクに完璧に分割できる、一部の専門的な作業に限られる。
- 3Dレンダリング: CGクリエイターが作成した3Dモデルに光と質感を加え、一枚の画像や映像として出力する作業。この処理はコア数が多ければ多いほど、単純に計算速度が向上し、作業時間が短縮される。
- 動画編集のレンダリング(書き出し): 編集ソフトのタイムライン上に配置した映像素材、エフェクト、テロップ、色調補正といった全ての要素を計算し、一本の高品質なマスターファイルとして生成する工程。これはCPU負荷が極めて高い処理であり、コア数が多ければ多いほど、この書き出し時間は劇的に短縮される。
- 動画のエンコード:レンダリングした動画ファイルを、YouTubeやTikTok向けなど、特定のプラットフォームや用途に合わせて別のコーデックに変換・圧縮する工程。画質とファイル容量を最適化するためのこの重い処理も、CPUの並列処理性能がフルに活かされる代表的なタスクだ。
- 科学技術計算・大規模なデータ分析: 天気予報のシミュレーションや、複雑な物理現象の解析など、膨大な計算を並列処理する必要がある分野である。
これらの作業を日常的に行うプロフェッショナルにとって、多コアCPUは投資に見合うだけの価値がある。しかし、あなたのPC利用はこれに当てはまるだろうか。おそらく、ほとんどの答えは「No」のはずだ。
「ワークステーション」と「コンシューマー向けPC」を分ける決定的差異
「だが、プロが使うワークステーションはもっと多くのコアを搭載しているではないか」
その通りだ。しかし、彼らが多コアCPUを選ぶ理由は、単にレンダリングが速くなるからだけではない。ここからが本題である。ワークステーション向けCPUが、我々が使うコンシューマー向けCPUと決定的に違うのは、「CPUが持つ帯域の広さ」、すなわちCPU直結のPCIeレーン数にある。
PCIeレーンとは、CPUと他のパーツ(グラフィックボード、SSD、拡張カードなど)を繋ぐ「データの通り道」だ。この通り道が広ければ広いほど、一度に大量のデータをやり取りできる。
- コンシューマー向けCPUの現実:
- Intel第13/14世代: CPU直結PCIeレーンは20レーン。グラボで16レーン、メインのNVMe SSDで4レーン使えば、もう空きはない。
- AMD Ryzen 7000/9000シリーズ: CPU直結PCIeレーンは28レーン。Intelよりは多いが、実際に利用できるのは24レーン程度である。
これに対し、ワークステーションやサーバー向けCPUはどうだろうか。
- ワークステーション/サーバー向けCPU:
- AMD Threadripper PROやIntel Xeonシリーズは、製品によっては100レーンを超えるとてつもない数のPCIeレーンを持つ。
この差が何を意味するのか。
ワークステーションでは、高性能なグラフィックボードの複数搭載、超高速なNVMe SSDによるRAID構築、高速なネットワークカードやキャプチャーボードの増設といった、膨大なデータ帯域を要求する使い方がされる。コア数が多くても、この「データの通り道」が狭ければ、各パーツは本来の性能を発揮できず、深刻なボトルネックを生む。
つまり、コンシューマー向けのハイエンドCPUは、たとえコア数を増やしても、PCIeレーン数が少ないために「なんちゃってワークステーション」にしかなれないのだ。サーバーとして使うにも、帯域や信頼性の面で力不足は明白である。
PCIeレーンだけでなく、メモリ帯域においてもこの差は歴然としている。 コンシューマー向けCPUでは通常デュアルチャネル(2ch)までの対応だが、ワークステーション向けCPUでは、クアッドチャネル(4ch)やオクタチャネル(8ch)といったマルチチャネルメモリに対応する。AIの学習や大規模なデータベース処理など、膨大なデータをメモリ上で扱うタスクにおいて、この帯域幅がボトルネックを解消し、処理速度を劇的に向上させるのだ。
一般向けのハイエンドCPUとは、あくまで「コンシューマー向け」という枠組みの中での最上位に過ぎず、その過剰なコア数は、CPUが持つ帯域とアンバランスな関係にあるのだ。
IntelハイブリッドCPUが抱える、スケジューラーの苦悩
さらに、近年のIntel CPUが抱える問題にも触れねばなるまい。高性能な「Pコア」と高効率な「Eコア」を組み合わせたハイブリッド・アーキテクチャは、一見すると画期的だ。しかし、その裏では深刻な課題が指摘されている。
それは、OSのタスクスケジューラーが、増えすぎたコアを完全に制御しきれていないという問題である。
本来であれば、OS(Windows)に搭載された「Intel Thread Director」がタスクの性質を見極め、PコアとEコアに適切に処理を割り振るはずだ。ゲームのような高いシングルコア性能を要求するタスクはPコアへ、バックグラウンドの軽い処理はEコアへ、といった具合に。
しかし現実には、ゲームの処理がEコアに回されてパフォーマンスが低下したり、特定のアプリケーションとの相性問題が発生したりと、その挙動は完璧とは言えない。ユーザーが意図しない動作に悩まされ、BIOS設定でEコアを無効化して問題を回避する、という本末転倒なケースまで報告されている。
ここで、「Macに搭載されるAppleシリコンも同じハイブリッド構造で成功しているではないか」という意見もあるだろう。しかし、両者を同列に語ることはできない。Appleはハードウェア(Appleシリコン)とソフトウェア(macOS)を垂直統合で開発している。これにより、特定のCPUアーキテクチャに最適化された、極めて効率的なタスクスケジューリングが可能になる。対して、無数のハードウェア構成に対応しなければならないWindowsでは、汎用性を確保する代償として、特定のCPUに完璧に最適化することが原理的に難しいのだ。
IntelがEコアの数をいたずらに増やしすぎているという構造的な問題も、もちろん無視できないが。
結論:賢いCPU選びとは、コストパフォーマンスの最適化である
我々は今、CPUメーカーが仕掛ける「コア数競争」という名のマーケティング戦略に、冷静な目を向けるべき時に来ている。
- PCの主な用途は何か? もしそれがゲームや一般的な作業なら、最新の8コアCPUこそが最良の選択肢だ。浮いた予算をグラフィックボードやSSDに回した方が、遥かに高い満足度を得られるだろう。
- あなたは本当に「全コアフルロード」の世界の住人か? もしあなたがプロのクリエイターやエンジニアで、CPUパワーが作業時間に直結するなら、多コアCPUへの投資を検討すべきだ。しかしその場合でも、コンシューマー向けCPUの限界(PCIeレーン数)を理解し、本当に必要なのはThreadripperのような真のワークステーション向けプラットフォームではないか、と自問する必要がある。
コア数が多ければ速い、という時代は終わった。これからの賢い自作PCユーザーは、「自分の用途に合った、バランスの取れたコア数」と、そしてCPUのもう一つの重要な側面である「帯域」という視点を持たなければならない。
今一度、あなたのPCの使い方を見つめ直すべきだ。そのPCに搭載された16個、24個のコアは、本当にその能力を発揮して輝いているだろうか。それとも、ほとんどの時間を退屈に過ごしているだけなのだろうか。その答えは、あなたの中にすでにある。
筆者のコメント
記事では、コンシューマー向けハイエンドCPUを「なんちゃってワークステーション」と評した。この評価は今も変わらないが、少し違う角度から、このCPUが持つ本当の価値について補足しておきたい。
これらのCPUは「かつては手の届かなかったプロの計算能力を、一般ユーザーの価格帯まで引きずり下ろした」という一点において、非常に大きな功績がある。
数年前まで、16コアを超えるCPUを使った高負荷な処理は、文字通り業務用の世界の話だった。数百万円クラスの専用ワークステーションを導入できる、一部のプロフェッショナルだけの領域だ。
しかし、Ryzen 9 9950Xのような製品は、その状況を一変させた。趣味の域を超えた動画編集、個人で請け負う3Dレンダリング、研究室から持ち帰ったシミュレーション作業など、「プロ用の機材を買うほどではないが、ミドルレンジCPUでは時間がかかりすぎる」という、絶妙なニーズを持つ層にとって、これ以上ない選択肢となったのだ。彼らにとって、これは作業時間を直接的に短縮できる、極めてコストパフォーマンスの高い投資と言える。
一方で、Intelの多コアCPUはどうだろうか。PコアとEコアを組み合わせたハイブリッド構成は、様々なタスクを同時にこなす汎用性には長けている。しかし、「全コアを100%使い切る」という特定の用途に限れば、AMDのシンプルな「全コアPコア」構成に分がある、というのが筆者の見解だ。レンダリングのような並列処理では、性能の低いEコアの存在や、OSのスケジューラーの挙動がボトルネックになり得る。純粋な計算パワーが欲しい場面では、全コアが高性能で足並みを揃えられる構成の方が、結果的に安定したパフォーマンスを発揮しやすい。
要するに、コンシューマー向けハイエンドCPUは、非常にターゲットが明確な製品なのだ。あなたの作業が、その有り余るマルチスレッド性能を享受できると確信しているなら、それは最高の選択肢になる。かつてのワークステーション級のパワーが、驚くほど手軽に手に入るのだから。
しかし、大多数のユーザーにとっては、本記事の結論は揺るがない。その予算は、ゲーム性能を直接引き上げるGPUや、より高速・大容量なストレージに回す方が、遥かに賢明な判断である。

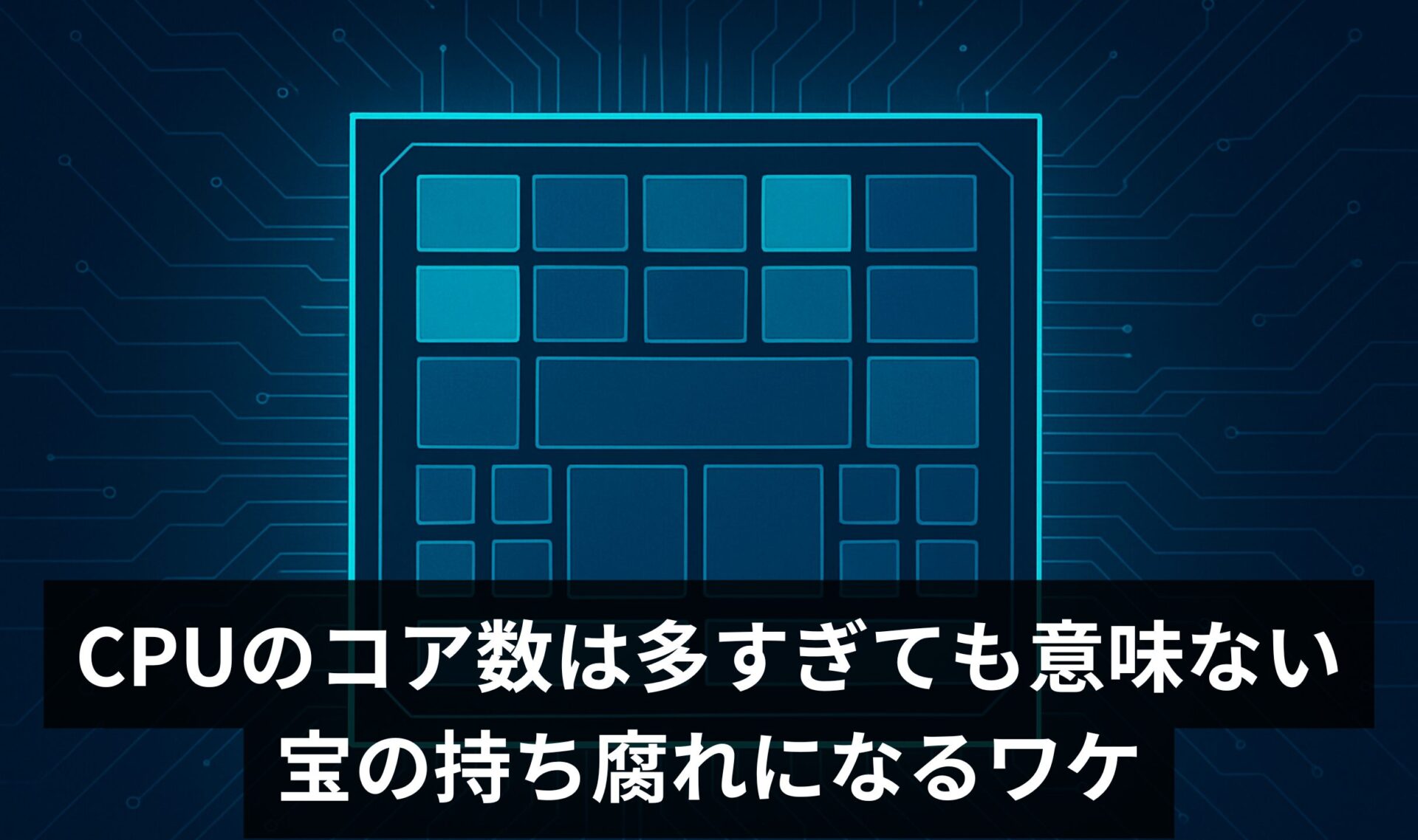
![AMD CPU CPU Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 正規代理店品 100-100000910WOF [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/21KtytBd+kL._SL160_.jpg)







コメント