IntelがArrow Lake(Core Ultra 200S)プロセッサー向けに導入した「200S Boost」機能がLinux環境下でもWindows同様、ほとんど性能向上をもたらさないことが明らかになった。専門サイトPhoronixのテストによれば、ハイエンドなDDR5メモリを搭載していない環境では、ゲームパフォーマンスの向上はほぼ誤差の範囲内にとどまっている。200S Boostの真価を発揮するには高速なDDR5-7200以上のメモリキットが必要であることが改めて浮き彫りになった。
Linuxでの200S Boostテスト結果
Phoronixが行ったLinux環境でのCore Ultra 9 285Kを使用したテストでは、200S Boost機能の有効化による性能向上がほとんど見られなかった。 このテスト結果はTom’s Hardwareが先日発表したWindows環境での検証結果と一致している。
テスト環境は以下の通り
- CPU: Intel Core Ultra 9 285K
- マザーボード: ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO(BIOS 1801)
- グラフィックカード: RX 7900 XTX
- メモリ: DDR5-6400 32GB
- OS: Ubuntu 25.04(Linux カーネル 6.14)
ゲームベンチマークでは、Counter-Strike 2やBatman: Arkham Knightで微小な向上が見られる一方、Dirt Rally 2.0では200S Boost有効時にFPSが大幅に低下(456 FPSから406 FPS)するという奇妙な現象も確認された。
生産性ワークロードについても、コンパイル系テストでわずかな高速化が見られる程度で、レンダリング系タスクには目立った変化が見られなかった。
200S Boostの真の効果はメモリ高速化にあり
Intelは200S Boost機能について「ゲーミング性能を約7%向上させる」と宣伝しているが、 実際にその恩恵を得るには条件がある。
200S Boostで大きな効果を得るには、DDR5-7200やDDR5-8000といった高速メモリキットの使用が不可欠だ。NGU(ファブリック)やD2D(ダイ間)インターコネクトのみのオーバークロックでは効果がほとんど得られない。
Phoronixが標準的なDDR5-6400キットでテストした結果、変化があまりにも小さくて「探さないと見つからない」レベルだった。Tom’s HardwareのWindowsテストでも、同じDDR5-6400メモリを使用した場合、16ゲームの平均でわずか0.8%のFPS向上に留まったという。
200S Boostの仕組みと位置づけ
200S Boost機能は以下の項目を高速化するBIOSプリセットとなっている
- ファブリック(NGU)クロック: 2.6GHzから最大3.2GHzへ
- ダイ間(D2D)接続: 2.1GHzから最大3.2GHzへ
- メモリ周波数: 6,400MT/s(3,200MHz)から最大8,000MT/s(4,000MHz)へ
この機能の最大の特徴は、メモリオーバークロックを含むこれらの設定が初めてIntelの保証対象となったことだ。 それ以前は、XMPプロファイルの使用や各種ファブリック速度の調整はCPU保証の対象外だった。
Intel自身は「低レイテンシーワークロード(ゲームなど)向けのパフォーマンスブースト」としてこの機能を位置づけているが、 実際の効果は限定的だと言わざるを得ない。
Arrow Lakeの課題と改善の取り組み
Arrow Lakeは発売以来、期待を下回るゲーミング性能で批判を浴びてきた。興味深いことに、Phoronixによる別の調査では、200S Boostを使用せずとも、発売から6ヶ月間のアップデートでLinux環境でのCore Ultra 9 285Kの性能が平均約6%向上していることが明らかになっている。
これはIntelが段階的に実施してきた改善策の効果だが、1月に行われたCES 2025でIntelは「修正により最大25%のゲーミング性能向上」を主張したものの、実際のテストではAMDに対する競争力や前世代との比較において意味のある影響は見られなかった。
Intel Client Computing GroupのVPであるRobert Hallock氏は、メーカーの内部期待値と実際のレビュー結果の差を縮めるための取り組みを続けていることを説明している。
筆者のコメント
Intel 200S Boostの実力を見ると、残念ながら「期待ハズレ」と言わざるを得ない。Intelが「7%のゲーミング性能向上」を謳う機能が、実際には高価なDDR5-8000クラスのメモリを導入しない限り効果がほとんど得られないとは、なんとも歯切れの悪い結果だ。
特に気になるのは、Linuxユーザーにとって恩恵がないに等しいという点だ。一部のゲームでパフォーマンスが低下するという現象も不可解で、この機能がまだ発展途上であることを示唆している。
そもそもArrow Lake(Core Ultra 200S)シリーズは発売当初から前世代のRaptor Lakeよりもゲーミング性能が低いという問題を抱えていた。200S Boostはその解決策として提示されたが、「DDR5-8000相当のメモリを積めば性能が出る」というのは、言ってしまえばただのメモリオーバークロックと変わらない。
この状況はIntelが直面している大きな課題を象徴している。単にマーケティングだけで「AI PC」や「200S Boost」といった派手なキーワードを打ち出しても、基礎となる性能が伴わなければユーザーの支持は得られない。実際、先日の決算発表で明らかになったように、消費者は高価な最新モデルより実性能と価格のバランスに優れた旧世代Raptor Lakeを選択している。
今後のIntelには、単なる保証付きオーバークロックプロファイルではなく、本質的なアーキテクチャの改善が求められるだろう。一方、ユーザーとしては高価なArrow Lakeと高速メモリの組み合わせに投資するより、コスパに優れたRaptor Lakeや競合AMDのRyzen 9000シリーズを検討した方が賢明かもしれない。
※本記事はPhoronix、Tom’s Hardware、PC Gamerなどの報道に基づいています。正式な製品情報は公式発表をご確認ください。

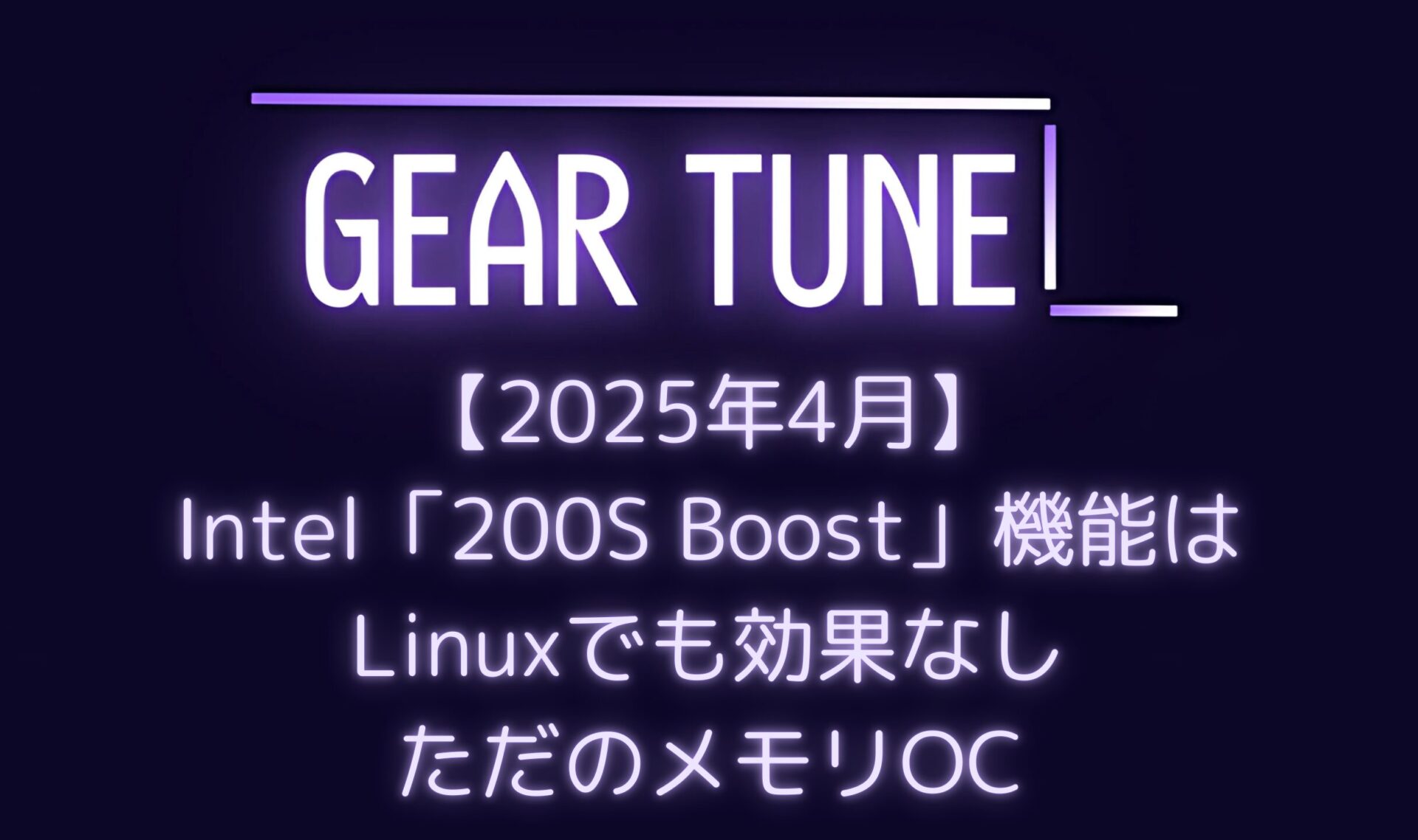
![100-100001404WOF [Ryzen 7 9700X (8C/16T、3.8GHz、TDP 65W、AM5、Radeon Graphics) BOX W/O cooler]](https://m.media-amazon.com/images/I/41tUy4Z4RpL._SL160_.jpg)



































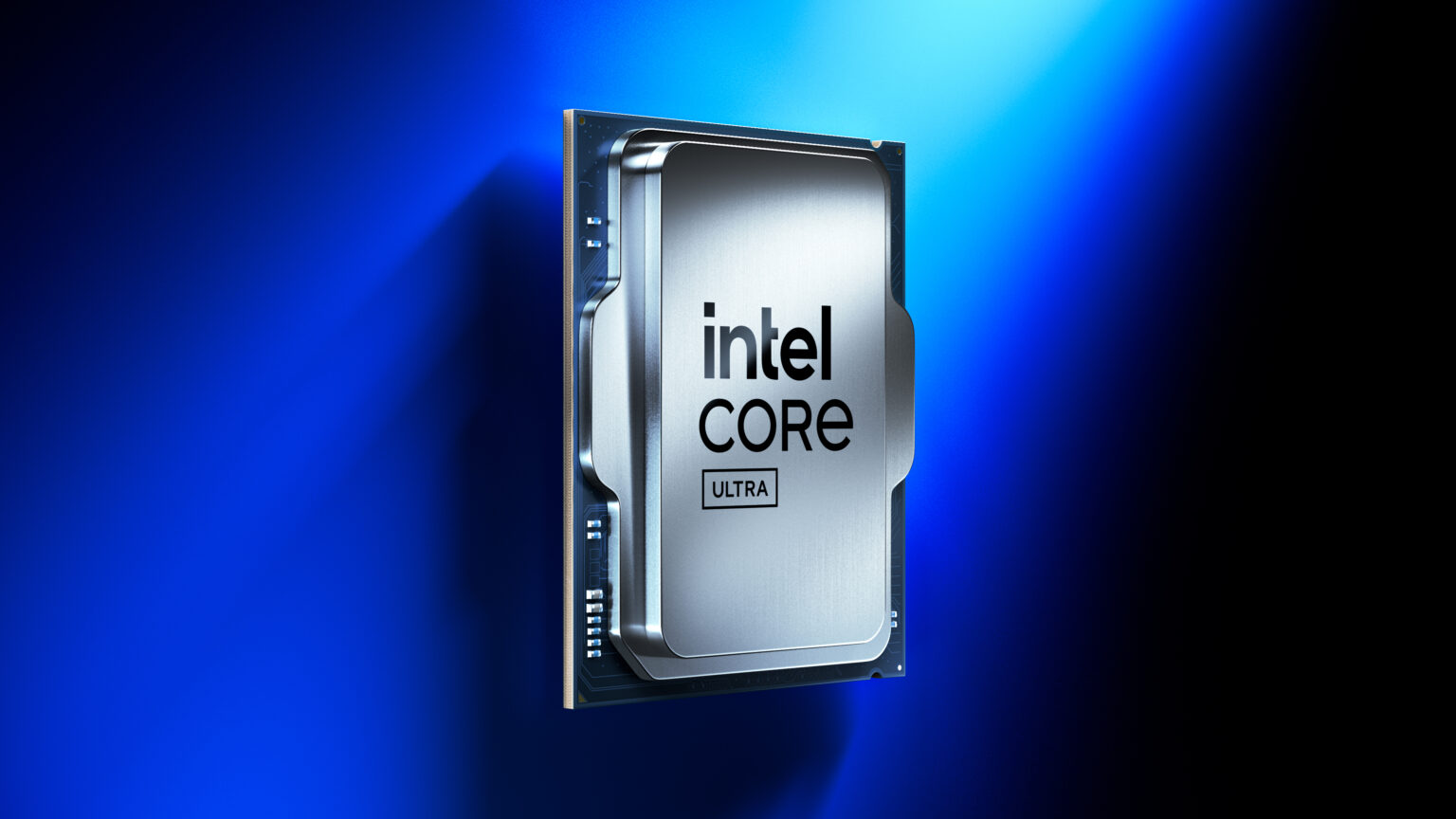
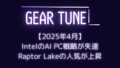
コメント